学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)
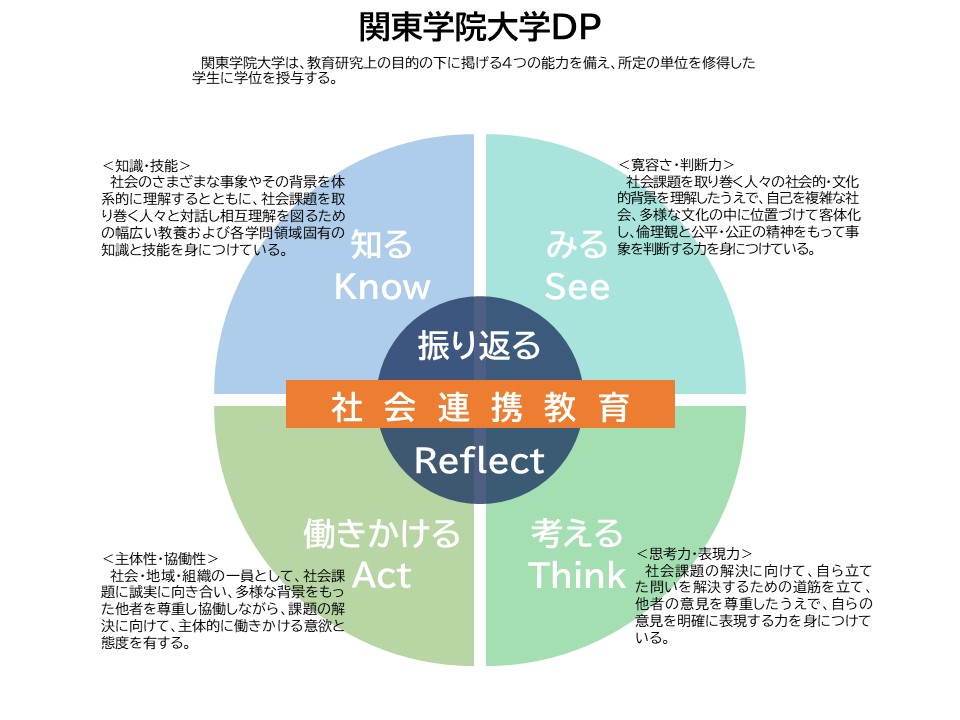
教育課程の編成・実施方針(カリキュラム・ポリシー)
関東学院大学は、学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)を達成するため、次に掲げる方針に基づき、教育課程を編成・実施する。
なお、本方針は、諸科学の進展や社会の変化、本学に対する社会の要請等を踏まえて、常に内容に改善・改良を加え、教育課程並びに教育指導体制の充実に努める。また、各授業科目は、公開授業制度や授業改善アンケートなどのFD(ファカルティ・ディベロップメント)活動によって、不断の努力をもってさらなる充実に努める。
これを踏まえて、各学部の教育課程の編成・実施方針(カリキュラム・ポリシー)を別に定める。
教育課程・教育内容
1 教育課程は、共通科目及び専門科目により体系的に編成する。
2 共通科目は、次の科目により編成を基本とし、各学部が教育課程を編成するうえで必要に応じて、分野や目的に沿って区分する。
<教養科目・総合科目>
・ 豊かな人間性を涵養する(建学の精神における「人」になる)ため、総合大学の特性を活かした幅広く深い教養を培う。
<キリスト教科目・自校史科目>
・ キリスト教及び自校史を学び、「他者への共感」「多文化理解」につながる教養を培う。
<キャリア教育科目>
・ 入学直後から実施する体系的なキャリア教育を通じて、社会的及び職業的自立を図るための能力と社会人たる素養を培い、生涯にわたって学び、社会に貢献できる人材を育成する。
<初年次教育科目>
・ 高・大の接続に配慮した導入教育により、大学での学びのための基礎力(スタディ・スキルやアカデミック・リテラシー)を養う。
<地域志向科目>
・ 学びのフィールドとなる「地域」について、自分の興味・関心・専門分野に応じた学びを通じ理解を深める。(地域に関する知識・理解)
<語学科目>
・ 英語を必修にさまざまな言語の体系的な学びを通じて、学生の海外派遣を促進するとともに、段階的に国際的な語学力、コミュニケーション能力を育成する。
<保健体育科目>
・ 健全で健康な生活を送るための基礎を学ぶ。
3 専門科目は、各学部の専門に沿って編成し、自己の専門分野に関する知識と方法論を身に付ける。
教育方法
1 講義を通じて、当該科目に必要な知識・技能を教授するとともに、書く・話し合う・発表するといった学生の講義への参加を積極的に導入する。
2 習熟度別等による少人数教育を推進し、きめ細かな教育を通じて、学習効果を高める。
3 PBL(Project/Problem- Based Learning)やサービスラーニング等の体験型授業を通じて、課題設定・実践的な解決能力を培う。
4 フィールドワーク、ボランティア、海外インターンシップ等の授業による社会参加の機会を通じて、多文化を理解し、他者と共生するための思考力・判断力を養う。
5 キリスト教への理解を軸とした幅広い教養を基に、アクティブ・ラーニングによる能動的な思考・判断の繰り返しと、他者との協働により、公平・公正な判断力を培う。
6 グループワーク、ディベート、プレゼンテーション等の協働による能動的な学びの場を通じ、傾聴の姿勢と、自らの立場、考えをわかりやすく発信するための能力を培う。
7 社会連携教育(地域、企業、自治体等との連携による教育)を展開し、社会をフィールドとしたPBLやサービスラーニング等を通じて、社会に参加する機会を創出し、社会参加への主体性を培う。
8 幅広い教養及び専門分野における知識、技術を基に、アクティブ・ラーニングやゼミナール等により、多様な背景をもった他者と協働するための規律性と柔軟性を養う。
9 キリスト教及び自校史への理解を基に、PBLやサービスラーニング等による実践的な課題解決のための学びを通じ、社会課題に対して誠実に向き合う姿勢を養う。
10 ICTを積極的に活用し、LMS(Learning Management System)を通じて、学生へのフィードバックや学習支援を行う。
学習成果の評価
学位授与方針の達成度を検証するために、学習成果の評価について次のように定める。なお、検証結果は教育課程編成や授業改善等に活用する。
1 学期中における理解度を把握するための小テスト及び学期末試験等を用いて、幅広い教養力や専門分野及び地域に関する知識・理解力を評価する。
2 レポートや論文・プレゼンテーションの成果に基づき、ルーブリックやポートフォリオ等の手法を用いて、建学の精神の実践・奉仕力、問題発見・思考力、倫理観、公平・公正な判断、協働力を評価する。
3 4年間の学びを通じて、学位授与方針に掲げた能力を総合的に評価する。
※ 教育課程の体系性や学位授与方針との対応関係はカリキュラムマップにより別途明示する。
入学者受け入れ方針(アドミッション・ポリシー)
関東学院大学は、キリスト教に基づく建学の精神を端的に表した校訓「人になれ 奉仕せよ」を掲げ、「キリスト教の精神に基づき、生涯をかけて教養を培う人間形成に努め、人のため、社会のため、人類のために尽くすことを通して己の人格を磨く」という教育方針を長年にわたって継承してきた。
本学の教育方針に共感するとともに、幅広い教養と専門性の高い知識・技能を主体的に身に付け、他者とともに次世代社会の創造と持続的発展へ貢献するための意欲と明確な目的意識を持ち、多様な背景を有する入学者を選抜するため、国内外問わず、世界のあらゆる地域から受け入れる。
そのために、培われた確実な基礎学力、経験や活動を通じて身に付けた能力、学ぶ意欲や人間性などを多元的に評価する以下の入学者選抜制度を有する。
1.一般選抜
一般選抜では、入学後に各学部の教育に必要な総合的学力を有する入学者を選抜するため、高等学校までの教育の到達目標とされる「知識・技能」「思考力・判断力」等を問う個別学力試験に重点を置いて評価する。また、高い英語能力を有する入学者を評価するため、英語資格・検定試験の結果についても評価の対象とした入学者選抜制度を有する。
英語検定試験のスコアを評価する入学者選抜制度では、「読む」「書く」「聞く」「話す」の英語の4つの技能を身に付けた入学者を選抜するとともに、「知識・技能」「思考力・判断力」等と検定試験に取り組んだ「主体性」を評価する。
2.大学入学共通テスト利用選抜
大学入学共通テスト利用選抜は、一般選抜とは異なる素養を持つ受験生を受け入れるための選抜制度と位置づける。入学後に各学部の教育に必要な総合的学力を有する入学者を選抜するとともに、高等学校までの教育の到達目標とされる「知識・技能」を中心に「思考力・判断力」等を問うため、大学入学共通テストで実施している幅広い教科・科目の筆記試験を利用し、その得点結果を評価する。
また、大学入学共通テストと、一般選抜における本学独自試験の試験結果の組み合わせによって、「知識・技能」「思考力・判断力」を評価する入学者選抜制度を有する。
3.総合型選抜
総合型選抜では、本学での学修を強く希望する者を対象に、従来の教科・科目の筆記試験だけでは測ることができない多様な能力やさまざまな活動や経験を通じて身に付けた能力や態度などを調査書、出願書類、レポートや小論文等の個別学力検査、プレゼンテーション、高等学校までに取得した資格・検定、面接等により、入学後に必要な総合的学力としての「知識・技能」「思考力、判断力、表現力」に加え、「主体的に多様な人々と協働できる態度」を観点に多面的、総合的に評価する。
また、実際の社会における経験や異なる文化的背景を持つ国での学習歴、本学の教育方針への深い理解を基にして、本学での学修を希望する者を受け入れるため、社会人、帰国生、外国人留学生、卒業生子女などを対象に、書類選考、面接、小論文等を通じて、基礎学力、活動履歴、日本語能力、学修意欲、適性等を中心に、「思考力・判断力・表現力」「主体的に多様な人々と協働できる態度」を多面的、総合的に評価する。
4.学校推薦型選抜
学校推薦型選抜では、本学での学修を強く希望する者を対象に、進学実績や教育連携、高等学校における学習成果等を鑑み、本学が指定した高等学校、日本語学校、機関等の推薦に基づき、書類選考及び面接を通じて、高等学校までの学習で身に付けた基礎学力や活動履歴、学習意欲等を中心に「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体的に多様な人々と協働できる態度」を多面的、総合的に評価する。
5.給費生選抜
給費生選抜は、高等学校までの教育の到達目標とされる「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体的に多様な人々と協働できる態度」を備えた入学者の才能を育成することを目的とする。各学部の教育に必要な総合的学力を有し、学業に意欲的に取り組む入学者を選抜し、給費生として奨学金を支給する。
また、高い英語能力を有する入学者を評価するため、英語資格・検定試験の結果についても評価の対象とする入学者選抜制度を設ける。さらに、選抜試験の成績優秀者のうち、一定の学力水準を満たす者を入学者として受け入れる。
英語検定試験のスコアを評価する入学者選抜制度では、「読む」「書く」「聞く」「話す」の英語の4つの技能を身に付けた入学者を選抜するとともに、「知識・技能」「思考力・判断力」等と検定試験に取り組んだ「主体性」を評価する。
6.編入学者選抜
編入学者選抜では、国内外の高等教育機関において一定期間在籍した者を対象に、書類選考、面接、小論文等を通じて、基礎学力、基礎的な専門分野の知識・技能、日本語能力、学修意欲、適性等を中心に、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体的に多様な人々と協働できる態度」を多面的、総合的に評価する。