理工学部土木学系鳥澤研究室の佐藤慎慈さん(工学研究科修士1年)、保坂邦彦さん(土木・都市防災コース4年)、松田蒼生さん(土木・都市防災コース4年)の3人が取組んだ論文が、一般社団法人建設コンサルタンツ協会 2024年度学生懸賞論文 特別賞を受賞しました。今回の学生論文は「未来を生きる若者たちが思い描く社会のカタチを聞かせてください」と銘打って提示された2つのテーマから、どちらか1つを選択して応募するもの。佐藤さんらは『―安全・安心な暮らしのために―安全・安心を実現するための防災・減災対策とは?』のテーマを選び取組みました。このテーマは、2024年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」を目の当たりにし「人類の脅威となる災害から生命、財産、暮らしや環境等を守るために、私たちは今何をし、次の世代に何を残すべきか」を考え論文に起こすもので、社会資本整備(インフラ整備)の観点から、どのような技術や制度が必要なのか、独自のアイデアを考察し提案するものです。
今回の論文で提案したのは『災害時の孤立集落救出に向けた空飛ぶクルマの活用』。令和6年能登半島地震において数多くの孤立集落が発生した石川県輪島市を例に、孤立集落への新たな救出手段について考察しました。地震直後からの孤立集落の発生状況とその推移を調査した結果、能登半島地震では孤立集落が実質的に解消するまで長期間を要したことが分かりました。能登半島の外浦を中心に大規模崩落が多発したことによって多くの集落が長期間孤立し、自動車専用道など規格が高い道路が少ないことで効率的な支援が困難であったことや、支援車両が集中したことによる渋滞が発生したことも原因となり、能登半島における道路ネットワークの課題がみえました。また、能登半島地震ではヘリコプターによる空路での救助活動も行われましたが、孤立集落周辺は山間で平地が少ない地形であったり、着陸するのに十分な場所が確保できなかったことで、結果として救助に時間を要したのではないかと考えました。そこで検証したのが「空飛ぶクルマによる救出の可能性」です。さまざまな資料やデータを用い、空飛ぶクルマによる救出でかかる時間を検証。陸路、海路、空路を組み合わせて救助が行われた能登半島地震よりも約2日早く孤立を解消することが可能であることを算出しました。
論文執筆にあたって、佐藤さんは「今回の学生懸賞論文は柔軟な発想でもOKとの事だったので、他の人が思いつかないような内容で攻めてみようと“空飛ぶクルマ”の活用を提案しました」と発想のきっかけを話します。しかし、空飛ぶクルマについての知識はゼロに等しく、3人で一から学ぶ必要があったといいます。また、空飛ぶクルマの概要だけでなく、関連する法律や様々な制限など、論文に取組む中で勉強しなければならない事項は多岐にわたったそう。保坂さんは「普段取り組んでいる自分の研究内容とはまた違うテーマだったのでとても新鮮でした。“空飛ぶクルマ”と聞いただけでワクワクして、楽しみながら取り組むことができました」と振り返りました。3人は実際に様々な検証を行ってみて、空飛ぶクルマを将来活用できる可能性は十分にあると実装に期待を寄せます。松田さんは「今回の自分たちの提案内容である災害時の活用も視野に入れた空飛ぶクルマの開発が今後進めば、単なる輸送手段としてだけでなく、土木・防災という点においても汎用性が広がると考えます」と未来の展望を語りました。
※学年は受賞当時のものです。
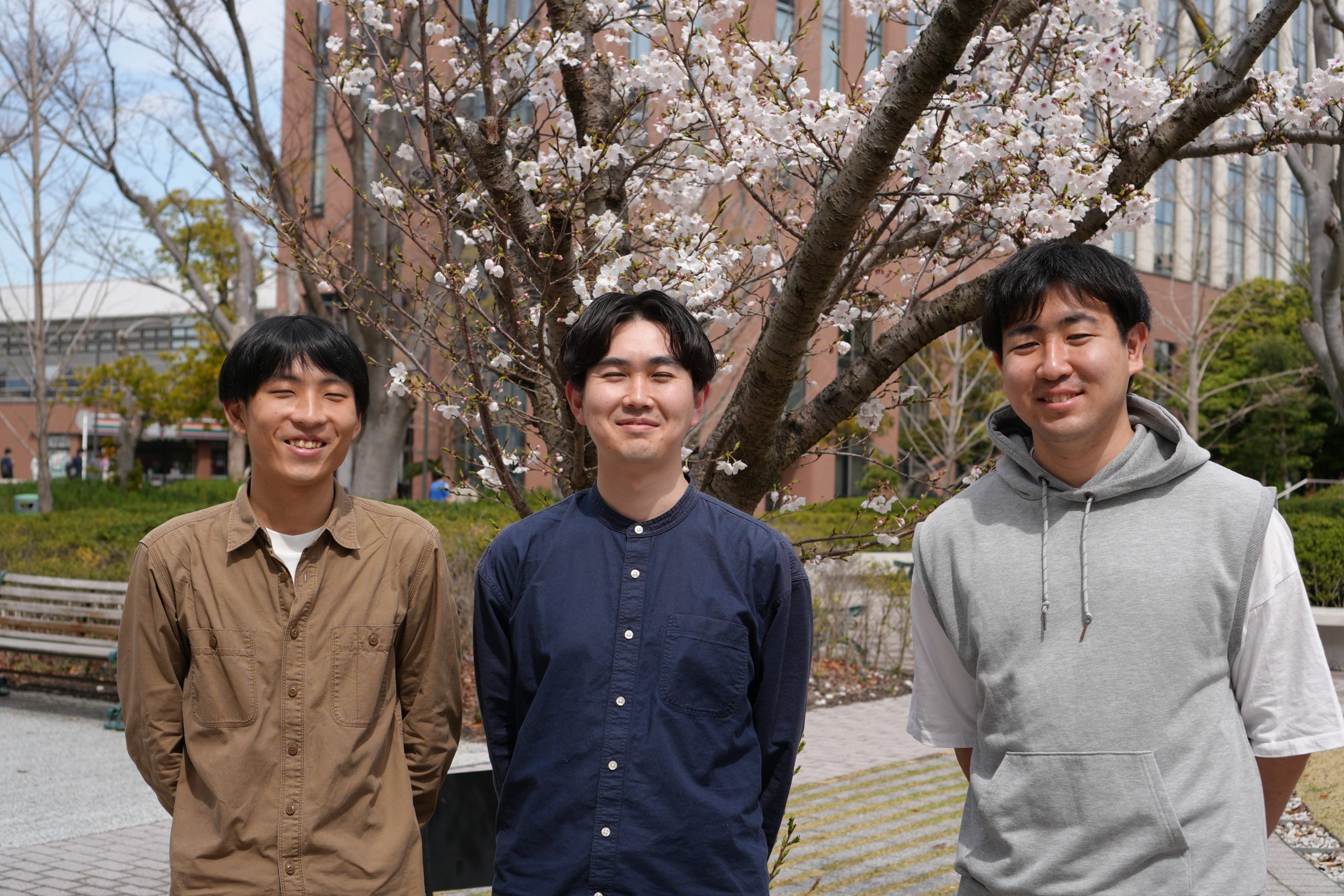
左から保坂さん、佐藤さん、松田さん
トピックスについての
お問い合わせ
関東学院大学 広報課
住所 〒236-8501 横浜市金沢区六浦東1-50-1
TEL:045-786-7049
FAX:045-786-7862
お問い合わせフォームはこちら

