8月30日(土)、理工学部情報ネット・メディアコース(2026年度より情報学部開設)元木研究室の学生が、「ドローンとAIを活用した次世代型密漁対策プロジェクト」の実証実験を開始しました。
この実験は、横須賀市、横須賀海上保安部と神奈川県立海洋科学高等学校の協働で行っているものです。神奈川県横須賀市、三浦市、逗子市、葉山町エリアでは、サザエなどの密漁者の人数が年々増加傾向にあり、昨年は61人、今年は既に58人が検挙されているという状況です。密漁者の取り締まりには、横須賀海上保安部職員が監視を行い検挙に努めていますが、その他の業務もあるなかで増え続ける密漁者を検挙するためにかける時間と人員が不足しています。そこで今回学生たちが取り組むのが、ドローンとAIを駆使した密漁者検知のシステムによる監視の自動化です。元木研究室では、AI密漁検知システムの構築を行っており、海洋科学高校の生徒が飛ばすドローンにAI機能を追加することで、上空からドローンカメラという目を通して密漁者の判別を行います。


7月5日にAIへ密漁者(pocher)を学習させるべく、海上保安官が密漁者に扮し典型的な密漁行動を再現しました。その様子をドローンで撮影し、観光客(leisure person)と区別するためのデータを収集。8月30日の実証実験では、そのデータで学習させたAIとドローンで実際に密漁が多く発生している海岸を監視し、密漁者の検挙に臨みました。ドローンで検知された人物は、密漁者か観光客に判別されます。密漁者の場合は、pocherという文字と密漁者度合の数値(最大値1)が画面に表示され、その数値を参考に検挙するかしないかの判断を行います。画面を見ながら、この反応は弱い、人がいないのに反応している、と性能を確かめる学生たち。主メンバーとして取り組む情報ネット・メディアコース4年の日下誠士さん、高見拓夢さんは「前回のデモで収集した密漁者のデータは、青色の網を持っているという特徴があり、今回は青色だけに反応し密漁者と判断してしまっている場面がありました。これから他のサンプルも集め、より正確に判別できるように仕上げていきたいです」と結果を振り返ります。AIに密漁者を学習させるために行われているのが、アノテーションと呼ばれる作業。ドローンで撮影した動画から画像を切り取り、密漁者と観光客を学生たちが手作業で分類し、学習データを作成するという作業ですが、精度の高いものにするためにはその分データも必要になります。学生たちは今回の実証実験の画像も学習させ、より正確に密漁者と判別できるよう挑みます。
今回のプロジェクトで開発された技術の実用化に成功すれば、海上保安本部職員の労力削減につながるほか、ここは監視されているのだという密漁者への抑止力効果が期待されます。貴重な海の資源を守るべく、元木研究室は今後も関係各所と連携し社会課題の解決に向け尽力していきます。


当日の様子は各メディアでも紹介されています。
・8月30日 テレビ東京 放送内容はこちら
・8月30日 NHK 放送内容はこちら
・9月1日 テレビ朝日 放送内容はこちら
・9月17日 テレビ神奈川 放送内容はこちら



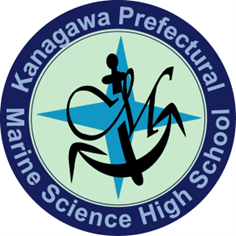
トピックスについての
お問い合わせ
関東学院大学 広報課
住所 〒236-8501 横浜市金沢区六浦東1-50-1
TEL:045-786-7049
FAX:045-786-7862
お問い合わせはこちら