11月8日(土)横浜・関内キャンパスにおいて、国際文化学部10周年記念シンポジウム「Yokohama Crossover-変わりゆく街に交差する物語―」が開催されました。本シンポジウムでは、横浜に造詣の深い3名の講師を迎えて、過去から現在へと変わり続けてきた都市・横浜の物語を語ってもらいました。のどかな海辺の村から、外国の文化を吸収し、多様なルーツを持つ人々が暮らす、港湾都市「YOKOHAMA」へと変身したその場所は、多文化共生がはらむ様々な課題を歴史的に背負った「生」の現場でもあります。「共生」の内実が問われる今だからこそ、歴史的な葛藤と先人たちの知恵に満ちた横浜の物語に、参加者たちは耳を傾けました。本シンポジウムのプログラムは3部構成となっており、本学国際文化学部教授の髙井啓介をはじめ、ノンフィクション作家の八木澤高明氏、東京外国語大学名誉教授の内海孝氏をお招きして、過去から現在へと変わり続けてきた都市「YOKOHAMA」の物語を語ってもらいました。また、今回のシンポジウムでは、手話通訳者による同時通訳が行われ、聴覚に障害のある方にも参加いただきました。
髙井教授の専門は、旧約聖書学・宗教学。大学で開催する『クリスマス・アカデミー』では、横浜と関東学院とクリスマスのつながりを地域の方々に知っていただくべく活動をしています。本シンポジウムでは、関東学院大学の校訓『人になれ 奉仕せよ』の実践として、『横浜における多文化共生の意義』と題し講演を行いました。髙井教授は「私たちは今、グローバル化の恩恵を享受する一方で、かつてないほどの分断と対立の危機に直面している」と話します。このような時代だからこそ、横浜の土地で多文化共生という土壌がいかに育まれてきたのか、また、その横浜の地で本学がどのような役割を果たすべきか、今後の国際文化学部の教育の展開について語りました。
ゲストにお迎えした八木澤高明氏は、写真週刊誌のカメラマンを経て現在はフリーランスのノンフィクション作家として活躍しています。横浜に生まれ、横浜を題材とした多数の著書を執筆しています。ご自身が生まれ育った横浜について、一般的に語られる横浜のイメージとご自身が見てきた横浜との違いについてお話頂きました。横浜の黄金町エリア一帯は、かつて大岡川の水運を利用した問屋街として繁栄していました。その後、関東大震災や第二次世界大戦によって街は激変し、京浜急行の高架下を中心に風俗店が軒を連ね独特な雰囲気が漂っていたそうです。立ちんぼ、ちょんの間、そして、エイズで亡くなった娼婦の話など、八木澤氏が黄金町エリアで撮影した写真と共に当時の様子が紹介されました。2005年、まちの浄化のため警察による一斉摘発が行われ、すべての特殊飲食店が閉店。現在では、空き店舗にアーティストを誘致し、アートによってまちを再生させる取組が進められています。八木澤氏が見た、普段はなかなか語られることのない、しかし、横浜の歴史の中に確実に存在する光の当たらない横浜の都市の風景、ストーリーが語られました。社会的弱者の視点から都市を見る重要性について、会場には深い静寂と共感が広がりました。
もう一人のゲストは、東京外国語大学名誉教授の内海孝氏です。横浜をはじめハワイ、ニューヨークなど地域研究および多文化交流史に携わってこられました。横浜との関係は、横浜にゆかりの深い原富太郎(号三溪)の未刊行の伝記『原三溪翁伝』を出版するために市民研究会を立ち上げ稿本を研究。その後の刊行に繋げました。原富太郎は明治から昭和前期にかけて生糸貿易で財を成した資産家、文化人で、横浜に『三溪園』を造園した人物として知られています。また、関東大震災の際には横浜の復興に尽力し、『横浜の恩人』と呼ばれました。本シンポジウムでは『砂利と生糸の近代史―眼に見えない意味を拓いて―』と題して講演頂きました。横浜の港湾都市としての成立を支えた生糸貿易や砂利の流通など、一見見落とされがちな「物」の歴史から都市のダイナミズムを解き明かしました。内海氏は「砂利や生糸は何気ないけれども今日の我々の生活を静かに支えているもので、その普及の起点は横浜にあった」と話しました。


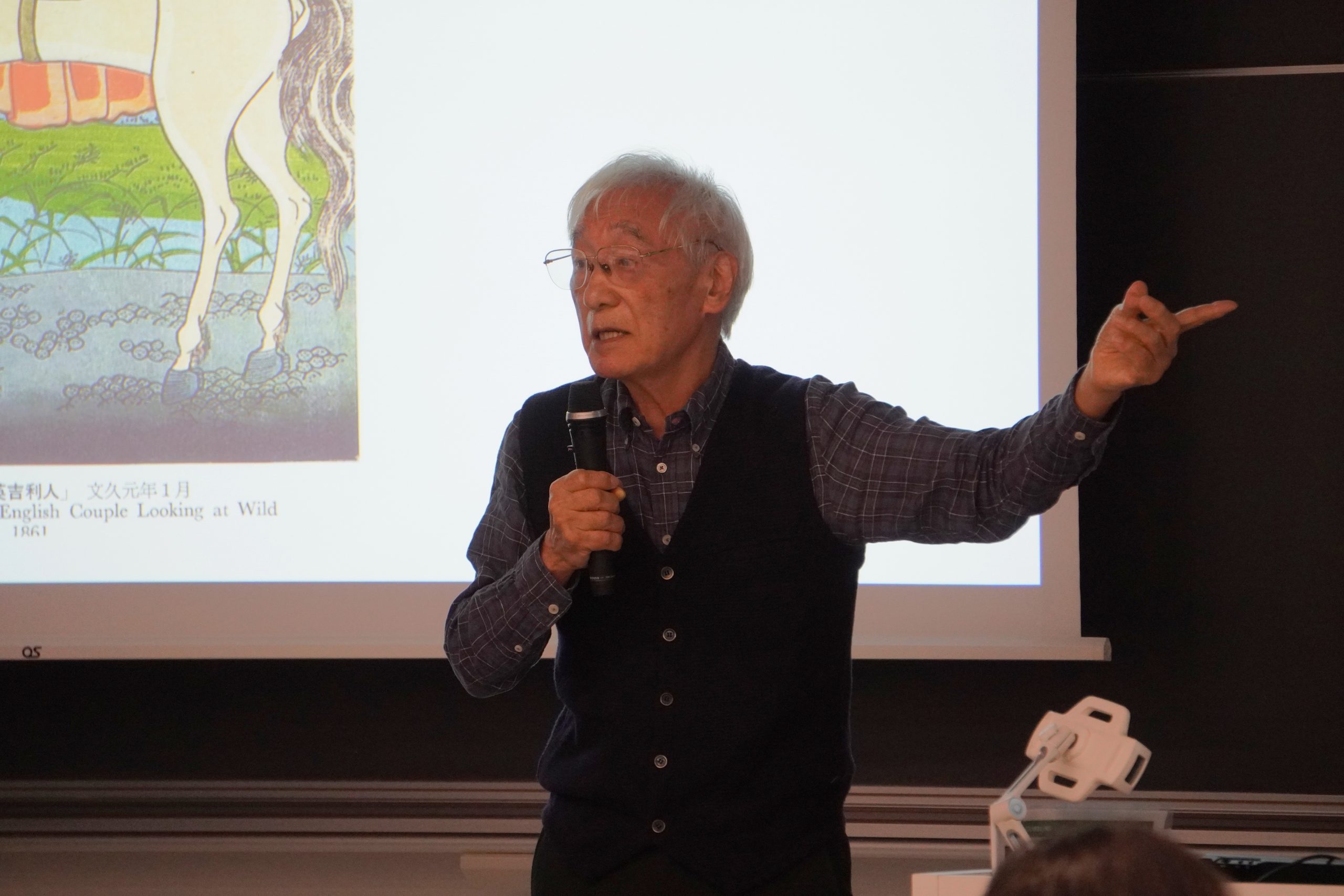

3名の講師が語る横浜の姿は、華やかな港町の表象だけでなく、葛藤・困難・多様な価値観が共存する「生きた現場」としての横浜を浮かび上がらせるものでした。
シンポジウムを通じて、国際文化学部がこれまで大切にしてきた“歴史と文化に根ざした学び”の重要性が改めて確認されるとともに、2026年度4月より2学科体制から1学科3コースへと教育内容を刷新する学部の新たな姿を見据え、多文化共生に寄与する教育・研究の深化に向けて貴重な視座が得られました。
今回のシンポジウムでは、日本手話(JSL)のろう通訳を導入するにあたり、聴者の手話通訳とろう通訳が連携する二段階通訳方式を採用しました。発表者の音声を聴者通訳者が日本手話に変換し、ろう通訳者がそれを自然な日本手話へ再構築して参加者に伝える方法です。事前にスライドや原稿を共有して専門用語や固有名詞を確認し、通訳チームとの打ち合わせで会場レイアウトや視認性、タイムスケジュールなどを調整しました。当日は、通訳者同士が細やかに連携し、ろう者参加者の反応に合わせて表現を調整することで、専門的な内容も分かりやすく伝えることができ、シンポジウム全体のアクセシビリティ向上に大きく寄与しました。
トピックスについての
お問い合わせ
関東学院大学 広報課
住所 〒236-8501 横浜市金沢区六浦東1-50-1
TEL:045-786-7049
FAX:045-786-7862
お問い合わせフォームはこちら