3月14日(金)、横浜・関内キャンパスにて公益財団法人 横浜企業経営支援財団(以下、IDEC横浜)との共同シンポジウム「環境課題をビジネスチャンスに~カーボンニュートラルが拓く新規ビジネスの可能性~」を開催しました。
近年、地球温暖化に伴う環境問題が顕在化していることから、日本でも未来への投資としてカーボンニュートラルの実現が宣言されています。また、経済産業省が中心となり、実現に向けたグリーン成長戦略が策定され、中小企業等にも具体的な取り組みが求められています。そこで、関東学院大学とIDEC横浜は、横浜市内の中小企業等が抱える経営課題やニーズを把握するIDEC横浜と、多彩な研究活動を行う関東学院大学が相互の資産を活用することで、環境技術や再生可能エネルギー分野などでのイノベーションを促進するべく包括連携協定を2024年に締結しました。
本シンポジウムでは、ゲストに横浜市都筑区に本社を置く株式会社スリーハイの男澤 誠 代表取締役、経済産業省イノベーション・環境局 大学連携推進室にて室長を務める川上 悟史氏をお迎えし、理工学部 応用化学コースの友野 和哲准教授、ファシリテータの関東学院大学 小山 嚴也学長(経営学部 教授)とともに、カーボンニュートラルの実現に向け、新たなビジネスチャンスについて探りました。

株式会社スリーハイ 代表取締役 男澤 誠氏

経済産業省イノベーション・環境局 大学連携推進室 室長 川上 悟史氏

理工学部 応用化学コース准教授 友野 和哲
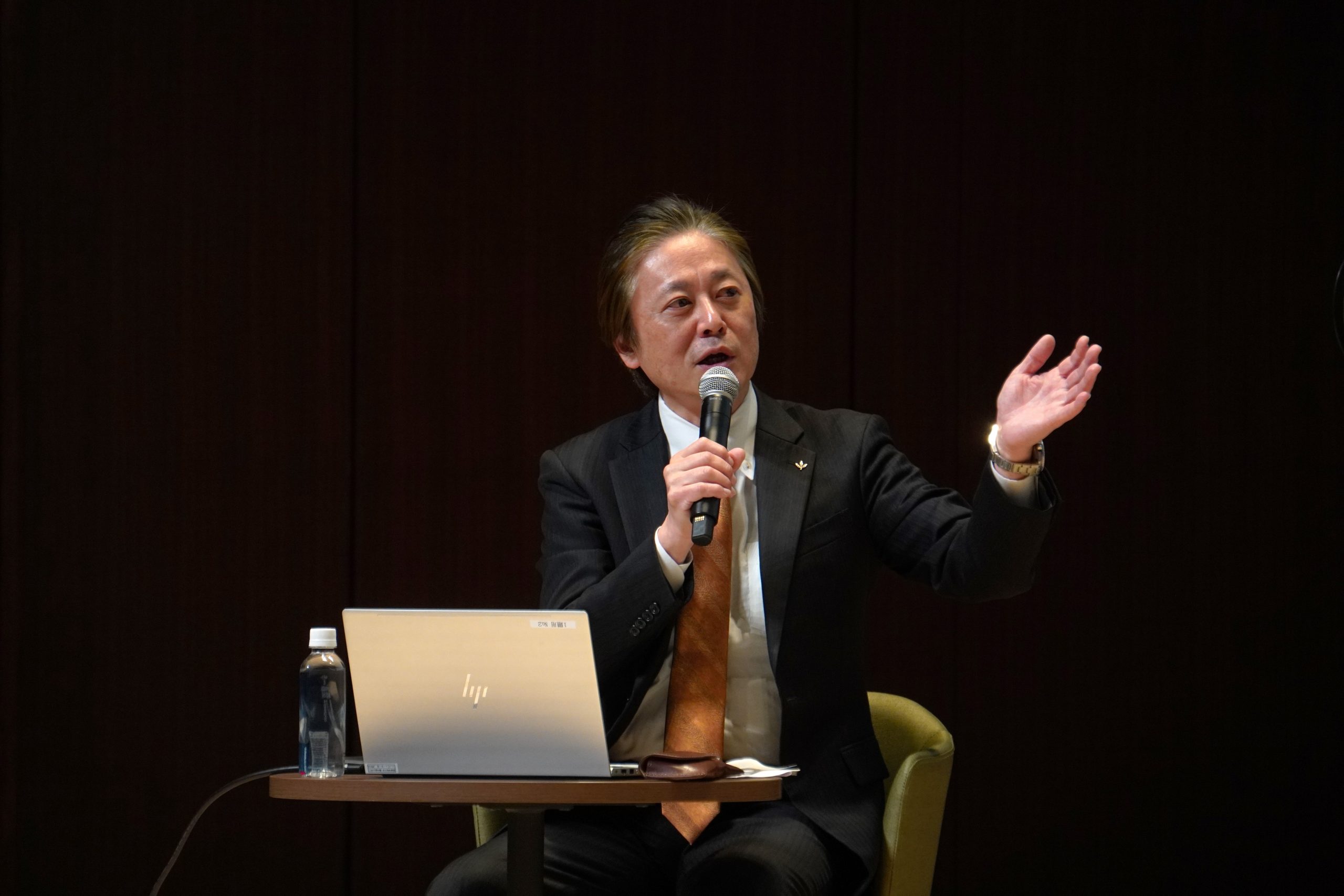
関東学院大学 学長 小山 嚴也(経営学部 教授)
株式会社スリーハイでは、産業用ヒーターの製造・販売を行っており、銅製品は企業の工場の生産ラインの設備など熱を保持する必要があるところに設置されています。最近では、お客さまからの「電気代が上がってしまって、コストが増えている。ヒーター本体の値段を下げるのではなく、電気代を抑えられる製品があると嬉しい」といった要望に応え、ヒーター設備用の断熱カバーを開発。断熱カバーにより、ヒーターの放出熱が軽減されたことで持続性があがっただけでなく、少ないエネルギーでの稼働が可能となり、工場内の生産率向上と電力消費量削減に繋がりました。また、工場内で廃棄される電熱線が巻きつけられていたボビンの分別を行っていた従業員から寄せられた「数が多く、分別するにも力作業のため負担が大きい。業者へ返すことはできないのか」との声を受け、業者へ確認したところボビンが返却されれば再利用できるということがわかり、両者のコスト削減と原材料削減、エネルギー消費削減に貢献することとなりました。このように、顧客の声や従業員の声を聴き、悩みを解決するために凝らした工夫がカーボンニュートラルの実現に向けたビジネスに繋がったと話します。
また、友野准教授は半導体などに使用されるシリコンの生産過程で発生するパンくずのようなゴミを資源化するため、シリコンくずの中からゴミを取り除くのではなく、ゴミの中からシリコンを抽出するリサイクル法を確立しました。さらに、蓄電機能だけでなく発電機能をも持つキャパシタ材料と呼ばれるエネルギーデバイスの研究も行っています。こうした技術を通してカーボンニュートラルに貢献できるうえ、企業で活用されればビジネスチャンスとなり得ます。


しかし、企業がこうしたビジネスを展開するには技術的な課題が残る場合があります。また、大学の研究者の優れた技術を実用化するまでにはビジネス上の課題が生じることもあります。そうした両者の課題を克服する一つの方法が、産学連携です。例えば、株式会社スリーハイが取り扱うヒーターは経年劣化に伴いヒーター内部の発熱線が断裂してしまう、という長年の課題を抱えています。新しい部品は受注生産のため納品まで1か月かかり、断裂してしまってから調達しようとするとその間の生産がストップしてしまうため、現在は代替品でなんとかカバーしています。「あらかじめ製品が劣化していることを察知できる仕組みがあればスムーズな対応が可能になるのですが」と話す男澤代表に対し、友野准教授は応用化学のアプローチで「例えば、熱であれば熱自体でも磁場でも検出できるため、磁力が弱っているところはもうすぐ切れそうだね、なんて察知することは可能です」と応え、シンポジウム中に解決の手がかりを見出すシーンがありました。
国内の産官学連携の促進を図るため、企業と大学のコーディネートを行う川上氏からは「大学の先生の話はやっぱり難しい、研究の内容が専門的過ぎてわからない、といったアレルギーを持ってしまっている企業の方も少なくありません。そういった企業と研究者をうまくコーディネートできたときに産学連携がうまれ、新たなイノベーションに繋がるのです」と話します。現状、企業の取り組みと研究者の研究はそれぞれが点と点のままで結びついていないことがほとんどです。ところが、直接会話をしてみると実は企業の悩みを解決できる糸口を研究者が掴んでいることが多いのだとか。一方で、企業の新たなビジネスチャンスが研究から生まれることも稀ではありません。小山学長は「今回のように、その課題は大学に相談してもらえれば解決できますよ、という可能性をどんどん広げていきたいです。企業には大学をもっと活用してもらいたいですし、企業と研究者がコミュニケーションを気軽に取れる場を設けたいと思っています」と意気込みます。
このシンポジウムを皮切りに、関東学院大学はIDEC横浜と連携を行いながら企業と研究者を繋ぎ、新たな価値を創出する機会を探っていきます。

トピックスについての
お問い合わせ
関東学院大学 広報課
住所 〒236-8501 横浜市金沢区六浦東1-50-1
TEL:045-786-7049
FAX:045-786-7862
お問い合わせフォームはこちら