研究報
Research Expectations

特集:日々の生活を支えるインフラ


研究報
Research Expectations

特集:日々の生活を支えるインフラ

明治維新を皮切りに、川を渡るために橋が架かり、安全な水を安定的に利用できるよう上下水道が整備され、インフラと呼ばれる生活基盤が急速に発達していきました。
それはライフラインに限ったものだけではありません。
広い意味では病院や公園、学校などの公共施設、社会の構造やあたりまえに存在している自然環境そのものが生活に欠かせないインフラと言えます。
それらは常に私たちの生活環境を支えており、失われた生活は考えられないほどです。
しかし、都市化や少子高齢化が進む現在では、まち自体の存続が危ぶまれている地域も少なくありません。
働き手不足や利用者減少により公共交通機関は減便を余儀なくされるなど、あたりまえの社会の存続に向けて課題は山積しています。
また、2025年1月に発生した下水道管の老朽化による道路陥没事故を筆頭に、高度経済成長期に
作られた構造物が一斉に耐用年数を迎えるという課題は、身近なところに潜む危険として全国各地で顕在化してきました。
わが国では、静かに生活を脅かすインフラにおける課題への対策が急務となっています。
私たちの生活は、この先どうなっていくのか。
あたりまえの社会を持続させるべく、社会が直面する課題に向き合う研究者たちがいます。
「今」を「未来」へ繋いでいくために。
関東学院大学の研究者たちが探る課題と未来の可能性についてご紹介します。
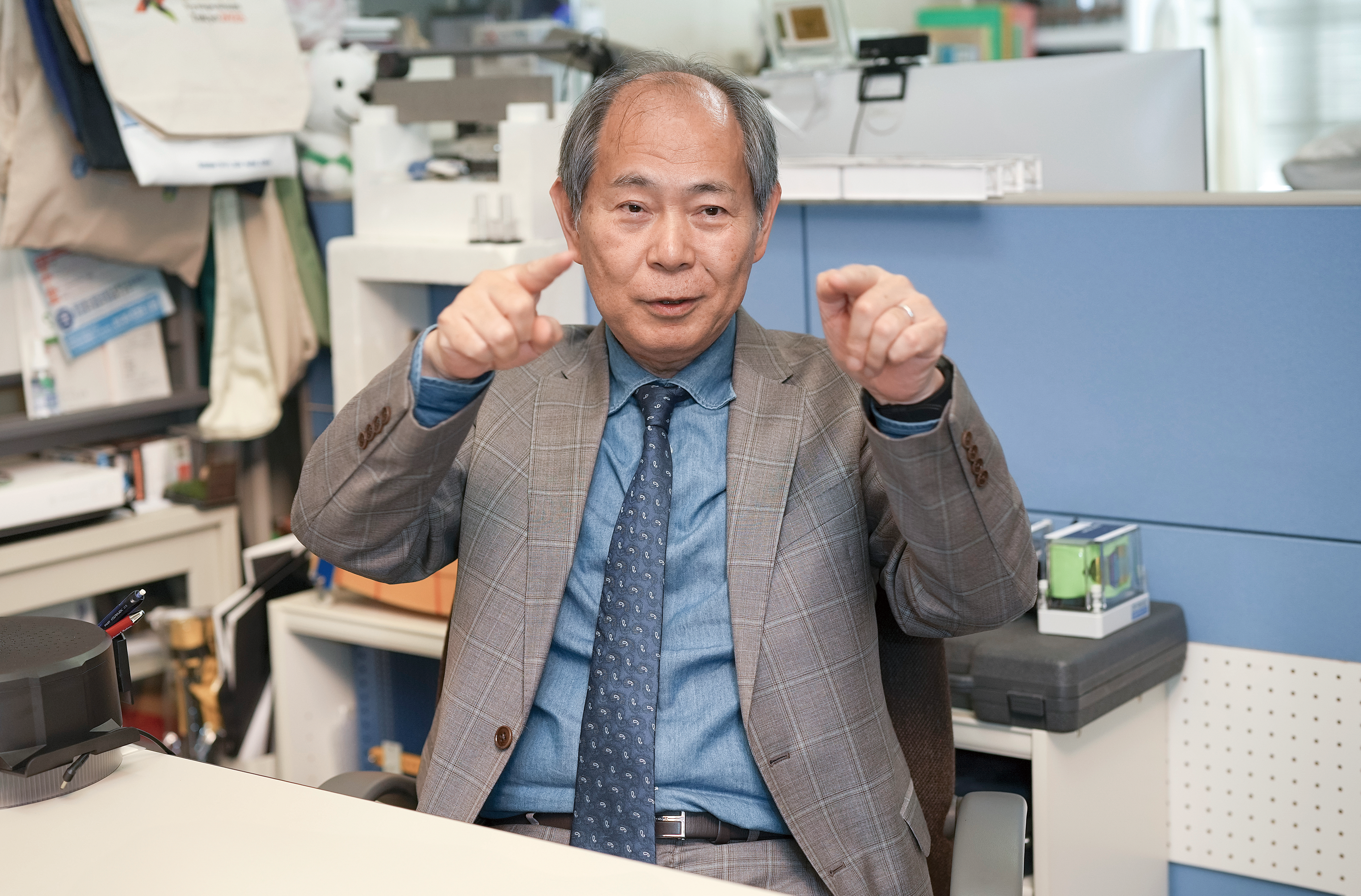
北原 武嗣 KITAHARA TAKESHI
理工学部 土木学系 教授
学位:博士(工学)
専門分野:社会基盤(土木構造・耐震・防災)

日本でも代表的な橋といえる、横浜近郊に存在する2つの橋、横浜ベイブリッジとレインボーブリッジ。どちらも橋の途中に高い塔が2本立ち、そこから何本ものケーブルが下の補剛桁(はしげた:道路部分にあたる)へと張り巡らされています。一見するとよく似ていますが、「実は構造的に『違う種類の橋』と言えます」と話すのは、理工学部 土木・都市防災コースの北原武嗣教授です。
橋にはいろいろな種類があります。横浜ベイブリッジは「斜張橋」と言われるもので、橋桁がメインの構造になっています。橋桁を両端で単純に支えるシンプルな構造、大昔からある丸太橋のような形式。ケーブルは「これらを補助する役割」とのこと。「ベイブリッジのような長大な橋の場合はケーブルの役割がかなり大きくなっていますが、一般的な斜張橋の発想としてはあくまで橋桁がメイン、ケーブルが補助という関係です」。
一方、レインボーブリッジは「吊橋」の1つで、ケーブルがメイン構造になります。斜張橋とは異なり、「ケーブルの引っ張る力で橋全体を支えていて、補剛桁は使用性のためのものです」。
「構造が変われば、橋の特性も変化します。最も長い橋を作るのにすぐれているのは吊橋で、『明石海峡大橋』はその代表。全長は3911m、支間長(橋を支える主塔と主塔の間)は、もっとも長いところで1991mに及びます。これは日本最長であり、世界でも有数の規模ですね」

横浜ベイブリッジ

レインボーブリッジ

さまざまな橋において、今大きな問題となっているのが「老朽化」です。道路やトンネルといった他のインフラと同様、これらは50年以上前から、高度成長期に日本で多数作られました。コンクリートは、年数が経つと劣化して弱くなる可能性が、ゴムは硬くなることがあり、深刻な問題となります。
実際に、海外では「老朽化により落橋したケースが出ています」とのこと。橋以外に目を移せば、日本ではトンネルの崩落事故も起きています。
「こうしたインフラは人々の社会生活を支える重要な施設であり、人や物の交通網でもあります。一箇所でも欠ければ大きな影響を及ぼしますよね。何より、命に関わります。だからこそ老朽化による損傷や崩壊は防がなければなりません」
そこで北原が研究しているのは、橋の現在の性能を評価し、劣化状況の推移を把握するシステムや手法の開発です。AIや機械学習を使って解析を行っています。
橋の劣化を評価するには、現状、専門家が目視でひび割れや腐食を観察する、あるいは、叩いて音を確認するといった方法があります。しかし、これらは熟練の技術者しかできず、何より内部の状況まで把握するのは難しいといえます。そこで北原の研究の1つでは、地震などにおける橋の振動を簡易な機材で計測し、その計測データなどから劣化状況を推定する手法を構築しています。橋を作った初期と現在の性能の変化、さらには将来の推移までを振動のデータから算出していくと言えます。

こうして劣化状況を把握することは、これからの社会にきわめて重要になります。なぜならどこの橋から修繕すればいいか、優先順位をつけられるからです。
「日本全国でたくさんのインフラが老朽化する中、一斉にそれらを修繕するのは現実的ではありません。どこも人やお金に余裕がないためです。私たちの研究で現在の劣化状況を一定でも評価できれば、早急に対応した方がよい部分がわかり、限られた人とお金でも効率的に行えるでしょう」
土木工学の分野で長く研究を続けてきた北原。「人々が安全・安心かつ快適に生活できる街や都市を作る。その実現に貢献するのがこの学問の役割です」と明朗に告げます。あわせて「環境にやさしく、持続的な社会基盤を作っていきたいですね」と笑顔を見せます。
そんな話をした後、関東学院大学の校訓「人になれ 奉仕せよ」を持ち出し、「この考えを具現化しているのが土木工学ではないでしょうか」と言います。社会を支えるため、人の暮らしを守るための研究なのです。
※本記事は2025年7月に作成したものです。