研究報
Research Expectations

特集:日々の生活を支えるインフラ


研究報
Research Expectations

特集:日々の生活を支えるインフラ


上野 淳子 UENO JUNKO
社会学部 現代社会学科 准教授
学位:修士(社会学)
専門分野:都市社会学、市民社会論
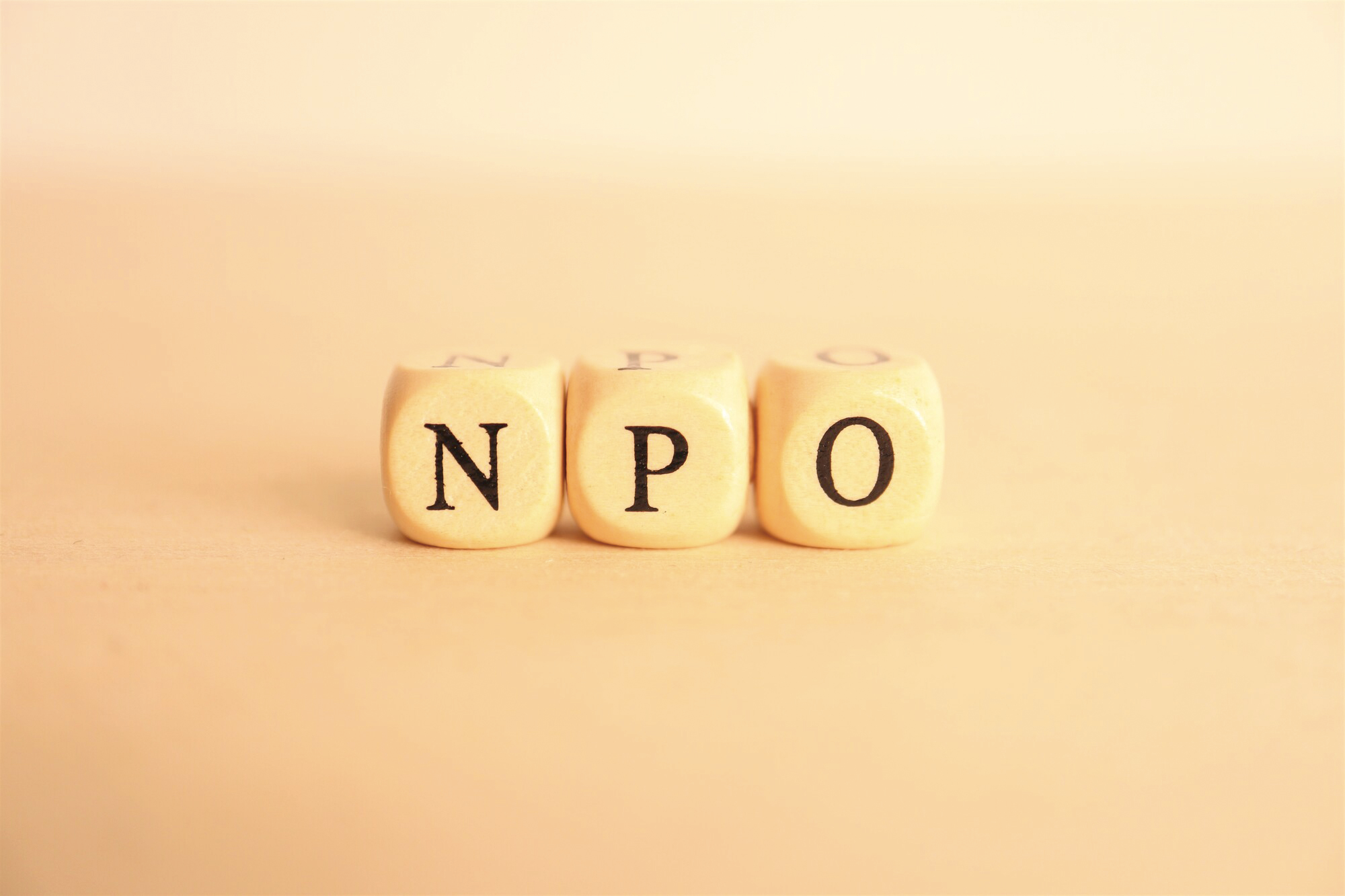
社会の土台となる仕組みや制度は、国や自治体だけが作るものではありません。市民の働きかけによって生まれることもあります。こうした「市民社会」のあり方を研究しているのが、社会学部 現代社会学科の上野淳子准教授です。
上野はもともと、都市開発に関する研究を行ってきました。超高層ビルやタワーマンションが密集する東京の都心空間は、どのような法制度や社会構造によって生み出されてきたかを考えてきたと言います。こうした研究を進める中で、次第に大都市の市民社会のあり方に興味が広がっていきました。
「都市の再開発では、市民の反対運動が起きることも少なくありません。しかし、そうした市民の主張が十分に受け入れられることはむしろ稀です。その点に課題を感じ、大都市の中でどうしたら市民のための空間や仕組みが作れるのかを考えるようになりました」
以来、調査の一環でさまざまなNPOの方から話を聞いたと言います。その過程で知ったのが、市民の運動によって市民のための仕組みや制度が作られた実例があるということ。たとえば1998年に制定されたNPO法(特定非営利活動促進法)は、さまざまな市民団体が協力して誕生したもの。
「市民団体であるNPOを支える仕組みを市 民みずから作っていたことに感動しました」

上野が研究対象にしているのは、1つ1つの市民団体そのものよりも、それらの団体同士が形成しているネットワークです。「NPO法を制定するまでの過程では、いくつもの団体が連携したり、特定の活動については新たなグループを作ったりと、目的や状況に合わせて柔軟なネットワークが形成されていました。このつながりこそが市民社会が生み出す価値のひとつだと感じ、注目するようになったのです」。
一例として、近年は「子ども食堂」や「フードバンク」などの食支援の活動を行う市民団体が増えています。実はこれらも、生協や農協、学校、企業などさまざまな組織が協力していることが多く、なかには「普段なら政治的に対立する立場にある団体同士が連携しているケースもあります」とのこと。このように、本来は一緒になりにくい団体が、大きな共通目的に向けてネットワークを形成するからこそ、新しい動きを作ることができます

こうしたネットワークは、1つ1つの活動を長く継続し、広げていくためにも重要です。「政府や企業とは異なり、市民団体は人もお金も潤 沢ではありません。素晴らしい理念を持った団体でも、活動を続けるには、外とつながり、支援してくれる仲間を見つけることが大切です」。
そこでポイントとなるのが、活動経験者とのつながりだと、上野は考えます。「市民活動は、社会問題に対する感覚を磨き、自分たちの力で何かを変えられるという実感をもたらします。だからこそ、経験者は、良い意味で“腰が軽い”のです。郊外の主婦たちが始めた生協活動からさまざまなNPOが生まれましたし、かつて共同保育をしていた母親たちがコミュニティの高齢化をきっかけに福祉NPOを設立した例もあります」。経験者が加わることで、社会への想いや信頼関係、活動のノウハウが次世代の市民に継承されていきます。
昔と異なり、近年は地域や住民のコミュニティが弱体化していると言われます。自治会、町内会の加入率は年々下がり、大都市では5割前後になっています。「かつては当たり前のようにあった地域の子ども会や町内会といった“中間集団”が少なくなっていますよね」。その中で、市民の活動は、子ども達が多様な背景をもつ人々と出会い「社会」を経験する場として今後より重要になるかもしれません。また、「ボランティアは民主主義の学校」と言われるように、利益を目的としない市民の活動は「民主主義を学ぶ場にもなる」と上野。だからこそ、これからも人々の活動を見つめ続けていきます。
※本記事は2025年7月に作成したものです。